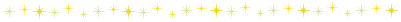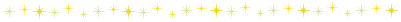1987年3月からは、ほぼ4組の公演を観る事になります。
4月は星組「紫子(ゆかりこ)/ジュビリー・タイム!」で、
u-tsuにとって初の星観劇でした。
因みにこの作品、わたるくんが宝塚で好きな作品らしい・・・
少なくとも初舞台の頃は、そうコメントがありました(^^)。
でもきっと、東京で観劇したのではないのでしょうねぇ。
だって4月にはわたるくん、音楽学校入学ですもん確か・・・
初舞台の年から逆算するとだけど。
「紫 子」は、もとは平安時代に書かれた作者不詳の
「とりかえばや物語」を、雪公演「大江山花伝」の
原作者の木原敏江さんが描いた「とりかえばや異聞」が
原作になっているそうです。
脚本・演出は柴田先生。
安芸の大名佐伯家の双生児の碧生(みどりお)と
紫子は別々に育てられたのだが、領主となった碧生が病気で
倒れた事から、紫子は兄の替え玉として家を守ろうとする。
その過程で、敵方の娘・舞鶴姫や刺客として送りこまれた吹雪、
佐伯に仕える定嗣(さだつぐ)らが絡んできます。
え〜っと、個人的にはあまり興味の無かった組といいますか(苦笑)。
あまり宝塚のことを知らない時だったので、トップさんに興味ないと
観劇とかしたいなぁと思わなかったものですから(^^ゞ。
宝塚自体をそんな感じで観ていたので、雪も花も月も、
最初は興味なかったんですよねぇ、実は・・・
もちろん、観続けていくうちにはお気に入りの生徒さんもできますけどね。
でも花組は初観劇が「夜明けの序曲」だったせいか、
また観たいなぁって、この頃は思っていなくて・・・
星組も、なんか、特別観たいなぁっていう気持ちがなくて、
友人に誘われたから、じゃぁ観てみるかっていう程度で(苦笑)。
「紫子」は感動するワケでもなく、つまらないワケでもなく、
だからって駄作っていうワケでもなく、どっちつかずに感じます。
男勝りで男児として育てられてきた紫子と、
病弱でたおやかな印象の碧生の、性別を間違えて生まれてきた
のではないか?っていうギャップは面白いと思うんですよ。
ちょっと設定は違うけどシェイクスピアに通じるものがあって。
で、決してキライな内容でもないしね、個人的には。
でもどこか違和感を感じていて、それが納得できないっていうか・・・
たぶん、スターさんの好き嫌いだと思うんですけど(苦笑)。
上手いけど、役としてはそれでイイのか?っていう・・・
演じ方なのかなぁ?もう、ホントに感じ方は十人十色ってくらい
違うんですけど、u-tsuにとっては役と役者が一致してないんじゃないか
って感じられて、イマイチ楽しめていなかったように思います。
当時、学生だったu-tsuには理由がよく判らなかったのですが、
成長して振りかえった現在は、たぶん、そんな理由だったのだろうと。
そんな風に感じてはいても印象に残った役はありました。
シメさん演じる金井定嗣。
佐伯に仕える近習頭とありますが、とっても真面目でカタブツな
ところがu-tsuの好みだったりしたもので(^^;。
シメさんが真面目にやればやるほど定嗣の人柄が表現されて、
不器用で可愛らしい人物だなぁと。
そして、ネッシーさん演じる吹雪。
紫子に想いを寄せ、それ故に忍びの仲間を裏切り
最期は紫子と共に死んでしまう・・・
忍びといえば一癖あって、その正体も謎っていうイメージがあるのに、
吹雪はそういったイメージがなく、爽やかで大らかな人物に感じました。
忍びらしくないから忍びなのか(苦笑)?
でもね、吹雪はわたるくんにピッタリな役だと思いますよ〜(^ー^;。
きっとね、ネッシーさんの吹雪よりも逞しい吹雪になるんじゃないかと。
あとねぇ、「花吹雪」っていう紫子が歌う曲が印象深いです。
寺田先生だったと思うんですけど、良い曲なんですよ〜。
峰さんの声とメロディが合っていて好きでしたねぇ。
ショーは、ミュージカル映画の曲あり、ロックありジャズあり
ラテンありと楽しい構成でした。
特に印象深い場面っていうのは・・・ないんですけど(苦笑)、
ラテンの場面はやっぱり好きですねぇ。
群舞でわーっと踊る場面が好きなので、自然と印象に残ります。
あとは、ブギ・ウギ・タウンっていう場面でドラム缶を
ドラム代わりに叩いて踊るっていう演出が印象に残ってるかなぁ。
楽しい明るい場面で好きでした。
当時はカッコイイ場面だなぁって思っていたんですけど、
今よ〜く思い出すとそうでもないかな・・・・
初めての星観劇で、取敢えず食わず嫌いではなくなりましたが、
かといって興味が出たわけでもなく・・・
でもネッシーさんやシメさん、シギちゃんはお気に入りでしたねぇ。
この3人の並びで舞台が観たいなぁと思いましたもん。
そして渋〜いオジ様、萬 あきらさんのファンにもなりましたよぉ。
昔からオジ様系が好きなu-tsuは、即ですよ(^^;。
なんだかんだいっても、それなりに楽しんだ初☆組でした〜。
 Galleryへ
Galleryへ
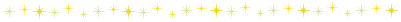
星組初観劇後、およそ5年振りの花組観劇をしました。
「遥かなる旅路の果てに/ショー・アップ・ショー」で、
高汐 巴・秋篠美帆トップコンビです。
ペーさんは以前雪組にいらしたのですが、雪時代はあまり
出演者について気にかけるほどのファンではなかったので、
この公演を観劇後しばらくして思い出したという感じです(苦笑)。
雪時代で観たペーさんは面白い役で、自然とその役を演じていて
今思い出だすと、とても芝居の間が独特で上手い人なんだなぁと
判ります。当時はそんな上手いとか考えるアタマないですから・・・
で、久々に観たペーさんの舞台なんですが、やっぱり独特で
宝塚では珍しい男役さんだなぁっていう印象が強くなりました。
大人の男性という役がとても似合うのですが、トップになられてからも
そういう役が多かったように思います。
ジャンルは確かに違うんですけど、なんか似たり寄ったりの
キャラが続いていたような感じがしてねぇ・・・勿体無い気が・・・
ペーさんの役作りのせいなのか、苦悩する部分が多い役だったからか
理由は不明なんですけど。
でも飄々とした、掴みどころのない雰囲気を自然と出せる部分は
大好きでしたねぇ(^^)。そこにちょっと不器用さが重なって、
カッコ良くないところが逆にステキだなぁっていう・・・
今の宝塚にああいう芸風ができる人っていないですよね。
コメディの間が、また絶妙でねぇ。
貴重な男役さんだったなぁ・・・と、思います。
相手役の秋篠美帆さんは決して華やかな雰囲気の娘役ではなく、
ダンスも踊れるなぁという風にはあまり見えず、歌も上手いという
印象はないのですが(苦笑)、役になりきっている舞台姿を観ると、
そんな物はこの人には関係無いのかなぁという感じがしました。
これがまさえちゃんなんだぁ、っていう気がすごくするんです。
常に一歩後ろっていう雰囲気の人なんですけど、
だからって目立たないというワケではなくて・・・
周囲との距離感がとても良いというか、自然体というか。
まさえちゃんの舞台は多く観ていませんが、
娘役として舞台に立つ姿は結構好きでしたねぇ。
古風な感じが良かったのかなぁ・・・そこが魅力だったのかも。
で、「遥かなる〜」はちょっと暗いお話で華やかさはありませんでした。
月の「パリ、それは〜」と比べると、どっちもどっちだな・・・
という感じですが、観ていて苦痛を感じなかったのは「遥かなる〜」です。
19世紀のロシアが舞台で、その貧民窟に君臨する男・サビーニンと、
モスクワ師団長の娘・エレーナとの波瀾に満ちた恋物語り・・・
花組にピッタリの大人のムード漂う作品でした。
作・演出は太田哲則先生。
太田先生って八百屋舞台での演出が多いんですが、この公演もでした。
「ショー・アップ・ショー」の作・演出は草野先生。
とてもテンポのいいプロローグが印象的なショー作品です。
黄色を基調にしたお衣装が爽やかで、最下級生に至るまで
エネルギッシュに踊っていました。
当時の最下級生は紫吹 淳さんの期だったかなぁ。
パンフの写真を見ると懐かしい顔ぶれがいっぱい・・・
この作品はバラエティに富んでいて見応えあるショーでした。
スピーディーなのでフィナーレまでがあっという間でしたねぇ。
とっても好きになったショー作品で、主題歌は今でも歌えます(^^)。
印象に残っている場面といえば・・・プロローグ。
始めて観るような構成のプロローグで、お衣装やセットは
そんなにハデでも豪華でもないのに、やけに印象深いんですよね。
そして中詰で、ボロを纏った3人の男が夢の世界へ入って
上流社会の紳士となって歌い踊るという場面も好きでした。
花組の品のあるダンスっていうのが、よく表現されている場面じゃ
ないかなぁと思います。いま思い出したらね。
それと、後半のビート・ラプソディーという場面。
大浦みずきさんを中心に、他は多くの若手で構成していた場面で、
途中音楽がなくて身体を楽器代わりにして踊るという演出が新鮮でした。
チームワークの良さが、観ていて気持ち良かったです。
確かこの場面は、団体賞を獲得したはずだと思ったんですけど?
どちらかといえば食わず嫌いな花組だったんですが、
個性的で大人なムードが魅力的だなぁと、
思ってたよりも好きになれました(^^ゞ・・・・
 Galleryへ
Galleryへ
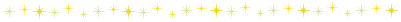
翌月の1987年7月には雪組観劇。
「宝塚をどり賛歌/サマルカンドの赤いばら」
大劇では初舞台生のお披露目公演でした。
この年の初舞台生といえば・・・
天海祐希さんが一番最初に名前が浮かんできます。
ずんこさん、ぶんちゃん、チャーリーさんなどなど、
注目されたスターさんが多く輩出されてましたね。
で、公演内容なんですが、先に日本物ショー上演。
春日野八千代さん、松本悠里さん、城 火呂絵さんが特出。
すごい貫禄と存在感、繊細で凛々しい舞いをみせてくれました。
基本的に場面は暗めなんですけど、日舞ってこういうものかと
思わされる舞でした。とても自分にはマネできないって感じ。
このショーで唯一気に入った場面といえば「月の抄」という場。
狂言で面白い内容でした。
他は誰が出ていてもどっこいどっこいな印象だったかな(苦笑)。
ただやっぱり雪組は和物の立ち居振舞いや化粧がキレイで
すーっと入りこんで行けます。
ただ、キレイだなぁ〜って観ていられるんですよね。
この頃は学生だったのでそんなに日本物には興味なかったし。
ホントに、キレイだな〜上手いな〜くらいですよ、感想は・・・
平さん、杜さんは凛々しいし、神奈さんは可憐だし(^^)。
目の保養ってトコロかな・・・?
お芝居はちょっと変わった演出がありました。
主要人物を演じている方々が手品をしながら歌ったり踊ったり・・・
宝塚の長い歴史の中でも初の試みじゃなかったかなぁ?
この作品は「千一夜物語り」のようにオリエンタルもので、
舞台はサマルカンド。
この国には姉妹の王女がいて、その花婿選びのため
各国から王子が参加のため集まってきた。
魔法使い修行中のイヴン・アラジンは踊りにばかり熱中し
修行に身が入らない毎日。
その有様を見た魔法使いの長老はサマルカンドへ修行へ行く
ことを進める。
砂漠の盗賊ハッサンも一国の王子に化けて参加することになり・・・
今思えばディズニー的要素が多い作品だったかも。
小さい子供が観ても充分楽しめる内容だったし・・・
でも大人が何度も観るにはちょっとキビシイものはあったな(苦笑)。
面白く楽しい場面が多かったりはするんですけどね。
修行中の魔法使いであり、有名なアラジンの曽孫のイヴン・アラジンに
扮したのは杜 けあきさん。
芸達者な杜さんにはちょっと物足りない感じの役ですが、
オチャメでおっちょこちょいなイヴンを上手く演じていました。
役の年齢を考えた時にちょっと若すぎる役じゃないか?とも
思うんですけど(苦笑)、当時は杜さん以外に考えられないかなぁと。
トップの平さんよりも印象が強い役でしたよ。
この作品ではイヴンが主役だと云えるくらいの人物でしたから。
初めて宝塚を観た人はイヴンが主役だと勘違いしてしまいそうです。
それくらい存在が描かれていますしねぇ・・・
すごいお得な役だと思います。
でも手品を披露する回数はイヴンが一番多かったかな。
かなりの集中力を要求されたと思います。
砂漠の盗賊ハッサンは平さん。
長身に黒の盗賊衣、マントはとってもお似合いでした。
何より、ハッサンたちの登場シーンがキレイなの!
カーテンが開くと舞台後方には砂漠が広がっていて、
盗賊たちがシルエットで浮かび上がるんですけど、
ちょうどハッサンの横顔のシルエットが影絵のようにくっきりと
キレイに浮かんで、まるで少女漫画のような横顔シルエット!
最近はああいう感じの場面の切出しがないんですよねぇ。
すごいステキなのになぁ〜。
ハッサンの見所といったらこの場面が一番に浮かぶu-tsuです。
やっちゃん(神奈美帆)とともちゃん(紫 とも)姉妹のおトボケ
ぶりが何とも可愛くて、ホントに世間知らずな王女様っていう
様が面白かったです(^^)。
おっとりした姉王女様も危険を察知した時は度胸満点という
ところがあって、ちょっと掴み所がないのも魅力的でした。
この作品では主題歌含め数曲メロディを覚えています。
内容も至って単純ですが、メロディラインも耳に馴染み易い
ものでしたね。
アラビア〜っていう音ってあるじゃないですか?
妖しい雰囲気で、でも耳にすーっと入ってくる音楽。
独特な世界が広がって童話に入りこんでいく・・・って感じでした。
キレイな歌なので、また聴きたいなぁって思うんですけど、
TCAとかで歌ってくれないかなぁ・・・
実はこの公演、当時3番手格だった一路真輝さんが休演しておりました。
肺に穴が開くとかいう病気で大劇でも途中から休演していたような・・・
代役は高嶺ふぶきさん。
日本物ショーは上級生の方だったように記憶しております。
さて、この公演中にもう一つ『実は・・・』っていう
出来事がありました。
u-tsuってば、初めてファンレターを手渡ししちゃったのぉ(*^^*)。
何を書いたか記憶はサッパリないんですけどねぇ。
お名前は出しませんが、『K.K』さんとしておきましょう(笑)。
最大ヒントは、この公演を休演していた方の同期生・・・
歌が上手で、どちらかといえば和物のほうがお似合いで得意かも。
出待ちをしている時はものすごいドキドキで、
楽屋から出てこられたところへいきなりお手紙を差出したもんだから
一瞬ビックリされてしまったんですけど、笑顔で受取ってくれました。
で、恐る恐る『お疲れ様でした・・・』と云ったら
ニッコリ笑顔で『お疲れ様Y』
と返して下さって、
とっても嬉しかったです(^▽^) ・・・ハートは嘘ですがね。
初めて宝塚を観た時は、自分がこんなことしちゃうなんて
微塵も思って無かったですよ・・・
しかもコレを期に、更に深みへ嵌って行くんですよね。
u-tsuの宝塚ファン歴はココから始まったというほうが正しいかも。
この2ヶ月後にはファンクラブにまで入会してますし・・・
こんな事になるなんてねぇ・・・未だに解せない感じ(苦笑)。
 Galleryへ
Galleryへ
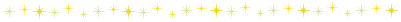
・・・to be continue
 Home menuへ
Home menuへ
 管理人 Topへ
管理人 Topへ