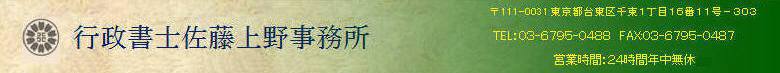遺言書作成
遺言書を作成する理由
・円満に相続してもらう1つの手段として、遺言書を作成しておくことも有効です。
「相続」→「争族」と揶揄されるように、財産相続では親族間でトラブルになりがちです。 財産を遺すご本人が、争いになるリスクが少なくなるよう手当をしておくことが、遺言をする目的の1つです。
また、
・遺産を渡したくない人がいる・たくさん渡したい人がいる・本来は相続人ではないけれど財産を分けてあげたい人がいる場合など、そういう思いを実現するためには遺言書を作成しておく必要があります。
相続でトラブルになるケースとは?
・相続人の数が多い場合や、親族の仲が悪い。 ・内緒で認知した子がいる。
・自宅以外にこれといった財産がない。など
※遺言が無い場合には相続人全員の話し合いが必要になるので、紛争に発展する可能性が大きくなります。
また、下記の場合は是非とも遺言をしておくべきでしょう。
・音信不通の子がいる。 ・息子の嫁に財産を与えたい。
・長く連れ添った内縁の妻がいる。 ・障害のある子が心配
・財産を与えたくない子がいる。
・夫婦2人で子供がいない。
例えば、夫婦で子供がなく、主な財産が住居としている不動産のみという場合に、ご主人が亡くなって、ご主人の兄弟が相続人となったような場合など、その兄弟に遺産を請求されると、残された妻は住居を売却しなければならなくなるかもしれません。しかし遺言によってそれを回避することができるのです。
なぜ、その遺言書をつくったのかも伝えましょう。
遺言を作ることによって遺産をもらう権利を無くす人や貰えるはずの遺産が減ってしまう人、その逆に取り分が増える人が出てきます。どちらも心の中は複雑な思いになるでしょう。遺言書を作成する際には、なぜそのような内容の遺言にしたのかを付言事項に記して、最後の思いを伝えることをお勧めします。
遺言は何度でも書き換えができます。
遺言は何度でも書き換えることができます。気が変わって、前に書いた内容を変更したいときは、新しいものを書けば前のものは無効になります。
とは言っても、正しい書き方をしないと、せっかく書いた遺言書も無効にされてしまいます。
法的に有効な遺言を書くためには、いくつか気を付けなければならないことがありますので、ぜひ、覚えておきましょう。
見た目が立派な遺言書は必用ない!
最近は書店等で遺言を書くための書籍や遺言作成セットが多数販売されています。
販売されているセットには高級な便箋とか封筒が入っていて、さぞ立派な遺言書が完成することでしょう。しかし見栄えの良い立派な遺言書は必要ありません。
遺言にしたい内容が決まったら、公正証書にすることをお勧めします。
※公正証書遺言を作りたい方は、書式等を覚える必要はありません。お近くの公証役場か
専門家にご相談されて、遺産をどのように分けたいかをお話しください。
ここでは、ご自分で自筆証書遺言を書いてみようと思われた方のために、簡単ですが遺言書の作り方を以下に紹介してみたいと思います。
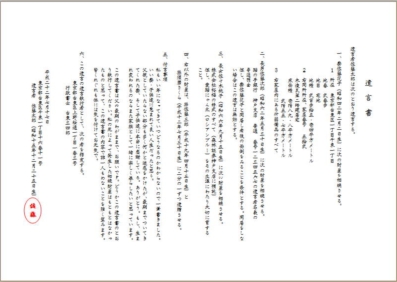 |
※電子メールでご請求いただいた方に「遺言書作成マニュアル」(pdfファイル)をお送りしております(電子メールで)。 スペースの都合上ここに掲載できなかった内容を簡単にまとめたものです。作成見本、チェックシートが付いています。
|
■遺言書の作り方■
遺言書には緊急の場合の特別遺言を除いては、通常3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
このうち自分ひとりで作れるのが自筆証書遺言、公証人と証人が関与して作るのが公正証書遺言と秘密証書遺言です。
■自筆証書遺言
自分の直筆で作成し、内容を秘密にできます。ただし、全て自署(手書き)で、日付の記入などについて厳格な要件があり、1つでも要件を満たしていないと無効となる可能性があります。
また、紛失したり、変造、隠ぺいされる怖れもあるとう欠点があります。
○自筆証書遺言作成の要点・注意点
・全て自書(遺言者本人の手書き)にて作成します。
・氏名と作成した日付を記入(2010年1月吉日などは×、2010年1月23日のように書きます)。
・押印する(認印可)。
・不動産、現金、預貯金など、それぞれについて何を誰に相続させる(あるいは遺贈する)のか
を具体的に書きます。(曖昧な内容は紛争の種になる恐れがあります。)
・作成した遺言書は原則本人が保管。(発見されない又は隠ぺいされる可能性あり)
・遺言書が発見され、開封するにきは家庭裁判所の検認が必要になります。
自筆証書遺言は手軽に簡単に作れる反面、法律上無効となる危険性が高く、実際に無効とされるケースも多いとききます。せっかく残す遺言が無駄にならないよう、また大切な方のためにも専門家に相談するのが一番です。
(お問合せは電話:03−6795−0488 またはメール:info@sato-ueno.com)
■公正証書遺言・秘密証書遺言
この2つの遺言は公証役場と証人が関与して作成します。ただし「秘密証書遺言」は、その内容が公証役場や証人にも分からないように作成され、保管等も本人が行い、費用や手間がかかるわりには自筆証書遺言と同じような短所があります。そのためか、実際にはほとんど利用されていませんので、ここでの説明も割愛させていただきます。
これに対し最終的に公証役場が清書して作成するのが公正証書遺言で、若干の費用はかかりますが、最も確実で安全な方法と言えます。遺言書を作るなら公正証書が一番のオススメです。
○公正証書遺言作成の要点・注意点(公正証書遺言)
・下書きを作成します。(公証役場で清書されるので手書きでなくても良い)
・内容の書き方については自筆証書遺言と同じです。
・証人2人が必要となりますが、ご自分で知人などに依頼できない場合は、公証役場で相談しま
しょう。(親族は証人になれません)
・原本は公証役場で保管されますので、紛失や隠ぺいの恐れがありません。正本と謄本がご本
人に交付されます。
※家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
以上、簡単ではございますが、もっと詳しく知りたい、遺言書を実際に作ってみたいという方は、電子メールまたはお電話でお問合せください。
(お問合せは電話:03−6795−0488 またはメール:info@sato-ueno.com)
遺言に関するご相談・手続き料金
●初回相談は無料。無料の意範囲を超えた場合、30分毎2,000円。メールのご相談は1通2,000円。
●自筆証書遺言(完成までの助言や確認、原案作成等) 30,000円(財産調査等が必要な場合は別途調査料がかかります)。
●公正証書遺言作成 40,000円(公証役場への手数料が別途必要。財産価額や相続人数により変わりますので見積りをとります)。
※事前に相談料が発生しているときは報酬額から相殺します。
※消費税が別途かかります。
■電話 03−6795−0488
■電子メール info@sato-ueno.com
初回のご相談は無料です。
ご相談はお気軽に